鉄筋は、建設業界で広く使用される重要な材料の一つです。鉄筋はコンクリートの引張強度を補強し、建物やインフラの安全性と耐久性を向上させる役割を果たします。この記事では、異形鉄筋の基本的な情報と、その径ごとの断面積と重量について解説します。
異形棒鋼の特徴
異形棒鋼は、表面に縦線方向のリブと軸線以外の方向の節を持ち、コンクリートとの付着力を高めるために設計されています。このリブと節のおかげで、鉄筋コンクリートは曲げやせん断力に対して高い抵抗力を持ちます。異形鉄筋は鉄筋コンクリート構造物のほとんどに使用され、その強度と耐久性を確保するために不可欠な材料です。
異形鉄筋の径ごとの断面積と重量
以下の表は、異形鉄筋の径ごとの断面積と重量を示しています。この情報は、設計や施工の際に非常に重要です。日本工業規格であるJIS G 3112にて規格化されています。
| 鉄筋径 (mm) | 断面積 (mm²) | 重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| D10 | 71.33 | 0.560 |
| D13 | 126.7 | 0.995 |
| D16 | 198.6 | 1.56 |
| D19 | 286.5 | 2.25 |
| D22 | 387.1 | 3.04 |
| D25 | 506.7 | 3.98 |
| D29 | 642.4 | 5.04 |
| D32 | 794.2 | 6.23 |
| D35 | 956.6 | 7.51 |
| D38 | 1140 | 8.95 |
| D41 | 1340 | 10.5 |
| D51 | 2027 | 15.9 |
使用頻度が高い径
よく使われる径はD13~D32です。コンクリートに応力を分散させてひび割れを防止するためにはD35以上の太径の鉄筋を粗い間隔で配置するより細径の鉄筋を密な間隔で配置した方が有利だからです。したがいまして、一般的にはD13~D32の鉄筋を使って設計を行うことが多いようです。
例えば、D35を250㎜間隔で構造計算が満足しなかった場合、次はD38で250㎜間隔でトライアルするのではなく、D25を125㎜間隔で検討するようにします。
そのようにして、D13~D32の検討で構造計算が満足しなければもっと太い鉄筋の使用を検討するということになります。
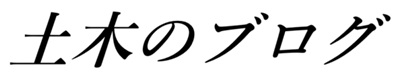


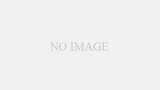
コメント