今回は自転車レーンについてです。まちを自転車で通るときに道路面に目印となる自転車レーンと呼ばれるものを見かけると思います。また、その標示にはいくつか種類がありますし、そのような標示がないところもあります。自転車をよく運転される方は気になるのではないでしょうか。それぞれは一体どのような違いがあるのかを解説したいと思います。
自転車の路面標示の種類
路面標示の種類として大きく分けて3つあります1つ目は「自転車通行帯(普通自転車専用通行帯)」2つ目は「矢羽根型路面標示やピクトグラム(法定外)」3つ目は「表示なし」です。「自転車レーン」と言う言葉は一般に分かりやすく表現された俗称であり専門的な用語ではありません。次に先の3つについて説明します。
1.自転車通行帯(普通自転車専用通行帯)

写真「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 平成28 年7 月 国土交通省道路局 警察庁 交通局」より引用
自転車通行帯(普通自転車専用通行帯)は、隣に走る自動車の通行空間を白線等によってしっかりと通行部分を分離したものです。自転車の通行帯として幅は通常1.5m以上確保(やむを得ない場合には1.0mまで縮小できる)されており、自動車の通行空間も必要な幅員が確保されているものです。3つの中では一番広い設定になっています。
このような設定としている場所の道路では、以下のような状況の道路となっています。
①自動車と自転車の両方の交通量が多い道路(目安として車4,000台/日以上でかつ、自転車500台/日以上の道路)
②自転車の交通量が多く、安全かつ円滑な交通を確保するため。(目安として自動車の速度が40㎞/h以上の道路)
③自動車と歩行者の両方の交通量が多い道路で、安全かつ円滑な交通を確保するため。(通勤・通学時などで自転車・歩行者の輻輳が時間的に集中して多くなるような道路。)
※ただし、上記①~③について新設道路で設計速度60㎞/h以上、既設道路で自動車の速度が50㎞/h以上の場合は自転車通行帯(普通自転車専用通行帯)ではなく、自転車道(車道と縁石等で区分)を整備する必要があります。
なお、「自転車通行帯」は道路構造令第9条の2に規定されており、「普通自転車専用通行帯」は道路法第45条第2項、道路交通法第9条第3項の規定に基づき「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に具体的な表示を示しており、第20条第2項の規定によりこの目的の道路標識に従って通行することを規定したものです。前者により幅員等の構造等を規定し、後者によって標識に従うことを明記しています。基本的に両者は同じものを言っています。
2.矢羽根型路面標示やピクトグラム(法定外)

写真「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 平成28 年7 月 国土交通省道路局 警察庁 交通局」より引用
「矢羽根型路面標示やピクトグラム(法定外)」は自転車と自動車の通行空間とは明確に分離されずそれぞれが混在する場合に、自動車に対して自転車が混在することを注意喚起するためのもので、青色の矢羽根が点々と書いてあったり、自転車の絵が描いてあったりするものす。
もともと、「自転車は『車両』であり車道通行が大原則」という観点からするとこれらが無くてもドライバーが注意して通行する必要があるのですが、注意喚起として考えられており「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」には無いものなので「法定外」とされています。設置条件は、道路構造令を読み解くと次に言うa~cの道路以外のd~fの場合に、矢羽根・ピクトグラムを表示します。
a.「1.自転車通行帯(普通自転車専用通行帯)」が適用される道路。
b.「1.③の逆で自動車と歩行者の両方の交通量が多い道路だが、自転車・歩行者が輻輳しない道路(⇒これは自転車歩行者道を整備してそこを通行することになります)」
c.「1.③の単に歩行者が少ないが自動車が多い。自転車交通量は関係なし(⇒これも自転車歩行者道を整備してそこを通行することになります)」
上記a~c以外で以下d~fの道路が歩車混在道路で矢羽根・ピクトグラムを表示となります。全て自動車の交通量が少ないケースです。
d.自動車の交通量が少ない第4種の道路(道路の両側にビルが立ち並ぶような都市部の道路です)
e.自動車の交通量が少なく歩行者の交通量の多い第3種の道路(道路の両側の建築物がまばらなな地方部の道路です)
f.自動車の交通量が少ないが安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある第3種の道路。
矢羽根・ピクトグラムの場合には自転車と自動車が混在するため、自動車の交通量が少ない場合のみに適用されます。混在するので自転車は矢羽根に沿って通り、自動車の運転者は自転車を避けて通りましょう。
3.表示なし
自転車の通行する箇所の路面標示が何もないところは、「自転車は『車両』であり車道通行が大原則」と言う考えと、上記以外で必要性が低い道路ということになると思います。道路構造令に記載はありませんが、a~f以外を書けば以下の道路となると思います。
g.歩行者の交通量に関係なく自動車と自転車の交通量が少ない第3種の道路で、安全かつ円滑な交通を確保する必要が無い道路。
まとめ
自転車レーンと言われる路面標示の種類とその設置に必要な道路の条件をによる違いをまとめてみました。その種類によってその道路の交通量との関係などの特性がお分かりいただけるのではないでしょうか。
また、少し分かりにくい内容だと思いますので、もっとわかりやすく表にまとめて後日追記したいと思います。
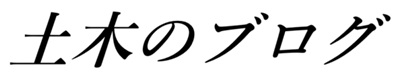

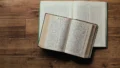

コメント